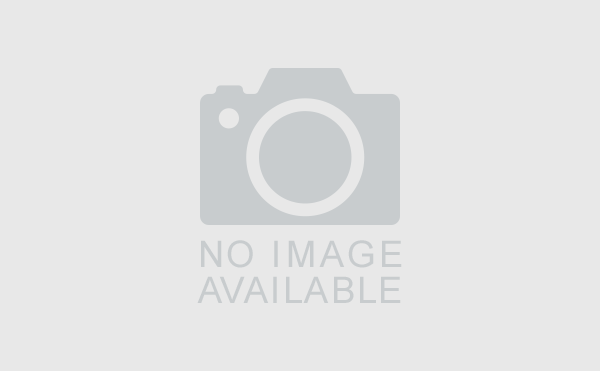【中学受験の疑問】中学受験の最難関校に合格しているのはどんな子か?
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
中学受験カウンセラー野田英夫です。
「うちの子は難関校に合格できるのかしら?」
中学受験を考えているお母様方なら、一度はそう思われたことがあるんじゃないでしょうか。
特に、周りの成功談やSNSなどで目にする優秀な子どもたちの話を聞くと、不安になる気持ちもよくわかりますよね。
しかし、SNSの情報はあくまで一部だということを忘れないでください。
SNSに投稿されるのは、うまくいった成功体験がほとんどです。
「うちの子、頑張ったけれど残念な結果だった」という話は、なかなか表には出てきません。
投稿しているのは、本当に優秀で、それを発信したい人か、あるいは実際はそうでないのに、ネットの世界で自分をよく見せたい、あるいは誇張したいという気持ちがある人のどちらかだと見方もできるでしょう。
みんながみんな、そんなにうまくいっているわけではないのです。
今回は、私が長年中学受験生とそのご家庭をサポートしてきた経験から、最難関校に合格する子の共通点について、特に進学校と大学付属校の違いに焦点を当ててお話ししたいと思います。
目次
■最難関校合格に天才は必須ではない
「最難関校に合格する子って、きっと生まれつきの才能があるんでしょう?」
よく耳にする言葉ですが、実はそうではありません。もちろん、一部には飛び抜けた才能を持つお子さんもいますが、多くのお子さんは「天才」というわけではないんです。
では、どんな子が合格を掴んでいるのか?
最難関校に合格する子には、大きく分けて2つのタイプが見られます。
■最難関校合格に見られる2つのタイプ
タイプ1:地道な努力を継続できる子
最も多くの最難関校合格者に共通するのがこのタイプです。
- 粘り強く問題に取り組める: 難しい問題に直面しても、すぐに諦めずに、ああでもないこうでもないと試行錯誤を繰り返します。
- 基礎を徹底的に固める: 派手な応用問題ばかりに目を向けず、地味な計算練習や漢字の書き取りなど、基礎を疎かにしません。そして、それがなぜ重要なのかを理解しています。
- 計画的に学習を進められる: 塾の宿題や課題だけでなく、自分で立てた学習計画をコツコツと実行できます。
このタイプのお子さんは、一見すると派手さはありませんが、日々の地道な努力が大きな実を結ぶことを証明してくれます。
タイプ2:知的好奇心が旺盛で、学びを楽しむ子
もう一つのタイプは、知的好奇心に溢れ、学ぶこと自体を楽しめる子です。
- 「なぜ?」を追求する: 与えられた知識をただ覚えるだけでなく、「なぜそうなるのだろう?」と疑問を持ち、自分で調べたり考えたりすることに喜びを感じます。
- 苦手分野にも積極的に取り組む: 自分の得意な科目だけでなく、苦手な科目も「できるようになりたい」という意欲を持って、前向きに学習します。
- 読書が好きで、知識が豊富: 本を読むことを楽しみ、様々な分野に興味を持つことで、知識の幅を広げています。
このタイプのお子さんは、学習が苦痛ではなく、むしろ探求のプロセスそのものを楽しんでいます。
■難関校合格に共通する精神的な成熟度とレディネス
そして、これら2つのタイプに共通して見られるのが、「精神的な成熟度が高い」ということです。
つまり、最難関校に合格する子の多くは、同年代の子どもたちと比較して、少し「大人びている」印象があります。これは、「大人びている」=「背伸びしている」ということではなく、精神年齢が高いことの表れだと言えます。
具体的には、次のような特徴が挙げられます。
- いま、自分がやるべきことがわかる: 指示を待つだけでなく、自分の課題や目標を理解し、主体的に学習に取り組めます。
- 自立していて、自律している: 親や先生に言われなくても、自分で学習計画を立て、それを実行する力があります。感情のコントロールもある程度できるため、学習に集中しやすいです。
- 論理的思考力が育っている: 複雑な問題文を読み解き、筋道を立てて考える力、つまり論理的な思考力が十分に発達しています。
この精神年齢の差、あるいは「レディネス(学習準備度)」の差は、確かに一朝一夕で埋まるものではないと感じるかもしれません。努力だけで全てを乗り越えられるわけではない、という側面があるのも事実です。
これは、そのお子さんの能力が低いということではありません。
単に、難関校の求める高度な論理的思考力や複雑な情報を処理する能力が、まだその年齢では十分に発達していないということが往々にしてあるんです。
いわゆる「学習年齢」が、中学受験で求められるレベルに達していない、という状況ですね。
「じゃあ、うちの子に難関校は無理なの?」
そう思われたお母様もいらっしゃるかもしれませんね。でも、安心してください。
この後、それぞれのお子さんに合った、もっと良い選択肢があること、そしてお子さんの可能性を最大限に引き出すためのサポート方法について詳しくお話しします。
■難関校における進学校と大学付属校の入試特性
最難関校と一言で言っても、その学校が進学校なのか付属校なのかによって、入試問題の傾向や求められる生徒像には大きな違いがあります。
難関“進学校”の場合:高度な精神年齢とレディネスが求められる
開成、麻布、桜蔭といった最難関“進学校”の入試問題は、6年後の大学入試(特に難関国立・私立大学)を見据えて作成されています。
難関“進学校”になればなるほど、6年後の難関大学への合格実績が学校の評価に直結します。
そのため、中学入試の段階で、将来的に難関大学に合格できる素地のある優秀な生徒に入学してもらいたいと考えています。
そうした背景から、入試問題は以下のような特徴があります。
- 難解な思考力・判断力を問う問題が多い: 単なる知識の暗記ではなく、深い思考力、複雑な情報を整理・分析する力、論理的に記述する力などが求められます。
- 精神年齢の高さが不可欠: 抽象的な概念を理解し、問題の本質を見抜く力は、精神的な成熟と密接に関連しています。
- レディネスが合否を分ける: 学習内容に対する準備度が整っているか(レディネス)が非常に重要です。
このため、難関“進学校”の入試では、前述の「精神年齢の高い、大人びた思考を持つ子」が圧倒的に有利となります。
難関大学“付属校”の場合:基礎学力とポテンシャルが重視される
一方、早稲田大学系属校、慶應義塾大学付属校、MARCH系列の大学付属校といった難関大学“付属校”の入試問題は、純粋な進学校とは異なる特性を持っています。
- 大学入試を直接的に見据えていない: 多くの場合、大学への推薦制度があるため、中学受験の段階でそこまで高度な思考力や知識を求める必要がありません。
- 基礎学力と応用力が中心: 小学校で学ぶ内容をきちんと理解し、それを正確に使いこなせるか、基本的な応用ができるかといった点が重視されます。
- 協調性や多様性も評価される傾向: 学力だけでなく、学校生活への適応力や、部活動・課外活動への意欲なども評価の対象となることがあります。
- 過度な精神年齢の高さは要求されない: 最低限の学習規律や自律性は求められますが、進学校のような飛び抜けた精神的な成熟度や、難解な論理的思考力は、入試の合否に直結しない傾向があります。
これは、難関大学“付属校”が、将来的にその大学で学んでほしい人材、つまり基礎をしっかり持ち、多様な能力と可能性を秘めた子どもを求めているからです。
保護者の皆様へ
無理強いは子どもの心を壊しかねません
もしお子さんが、今の段階で最難関進学校の求めるレベルに達していないと感じる場合、保護者の方がその状況を認めず、無理に学習を強いると、子どもの心に大きな負担をかけてしまう可能性があります。
極端なケースでは、「教育虐待」に発展してしまうことすらあり得ます。
お子さんの学習意欲が低下したり、自信をなくしたり、ひどい場合には学校に行きたがらなくなったりするような兆候が見られたら、それは赤信号です。
■お母様にできること
お子さんの「今」に寄り添い、成長を待つサポートを
いかがでしたでしょうか。最難関校合格には、単なる努力だけでなく、お子さんの精神的な成熟度やレディネスが深く関わっています。そして、目指す学校が進学校なのか付属校なのかによって、入試の特性と求められる力が異なることをご理解いただけたかと思います。
お母様にできることは、お子さんがどちらのタイプであっても、その子の「良さ」を最大限に引き出すサポートをしてあげることです。
- 地道な努力をねぎらい、具体的な成果を褒めてあげましょう。
- 知的好奇心を刺激するような問いかけをしたり、学びの機会を増やしてあげましょう。
- お子さんの精神的な成長を促すために、日頃から自分で考えて行動する機会を与えましょう。
もし今、お子さんが難関“進学校”のレベルに達していないと感じても、それは決して能力の限界ではなく、「まだその時期ではない」と捉えることが、お子さんの健やかな成長を支える上で何よりも大切です。
お子さんの個性を理解し、その「今」に寄り添いながら、中学受験という道のりを一緒に歩んでいってください。
ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいね。
では、また!
中学受験カウンセラー 野田英夫でした。