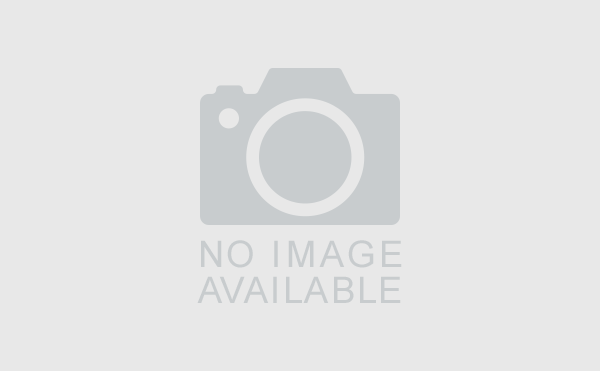【中学受験の疑問】志望校に落ちる家族の特徴【3選】
皆さん、こんにちは
中学受験コンサルタントの野田英夫です。
今回は、多くの中学受験家庭が最も不安を感じるテーマ、
「志望校に不合格になる家族の特徴」について、
これまでの経験から分析した構造的な問題点を3つの特徴としてお話ししたいと思います。
【特徴①】 目的を見失い、「手段」に振り回される家族
志望校に落ちる家族の最も大きな特徴は、
本来の「目的」と「手段」を混同している点にあります。
塾の成績への固執:
「志望校合格」(目的)と、塾のクラスアップや成績向上(手段)が、いつの間にかすり替わっています。
塾の成績は塾内での相対評価に過ぎず、志望校の入試問題が解ける力には直接に結びつかないにもかかわらず、その数字に一喜一憂し、冷静な戦略的な判断ができなくなっている。
非効率な学習:
クラスを上げるためのテクニックに偏り、インプットばかりの学習になっている。
志望校合格というゴールから逆算した学習計画(戦略)がなく、無駄の多い「積み上げ式学習」に終始している。
戦略的な学習の欠如:
目標から逆算した計画を立てられず、行き当たりばったりの学習になっている。
【特徴②】 「親塾」で子どものモチベーションを潰す家族
不合格となる家庭の多くは、親が子どもを「外的コントロール※」し、精神的な負荷をかけている。
外的コントロール※とは?
子どものやる気や行動を、報酬や罰則といった外部からの力で動機づけようとすることです。
親子関係の悪化と叱責:
親が成績の浮き沈みに感情的になり、外的コントロールを発動している。
特に、「勉強ができない」と過度に叱りつけることで、子どもを委縮させてしまう。
親が勉強を教える「親塾」は、親子喧嘩の原因となり、子どもの主体性を奪う「百害あって一利なし」の行為です。
モチベーションの低下:
子どもが「親にやらされている」と感じることで、受験が「他人事の受験」になっている。
その結果、学習へのやる気が低下し、忍耐力や自信を失い、難しい問題に直面するとすぐに諦めるようになってしまいます。
大手塾への依存:
親が「塾に行かせているから大丈夫」と放置したり、逆に大手集団塾の言いなりとなり、塾のシステムや競争原理に巻き込まれている。
【特徴③】 「基礎の穴」と「甘い基準」を放置する家族
合格の鍵となる実践的な対策と学習への姿勢が欠けている。
基礎の穴の放置:
「わかったつもり」で先に進み、基礎が固まっていない状態を放置している。
過去問対策の軽視:
志望校の過去問を解く回数が少なく、入試の傾向と対策ができていない。
甘い基準:
学習の精度や学習時間に対する基準が低いため、「これくらいでいいだろう」という甘えが学習の質を下げている。
まとめ:成功は「自分受験」の徹底
志望校合格は、隣の子に勝つことではなく、受験生であるお子さん自身が「自分受験」を意識することです。
成功の鍵は、「塾の成績」に振り回されず、中学受験する家族の「目的」を明確にし、志望校というゴールから逆算した「戦略的な学習」を徹底することにあります。
お子さんの「自分受験」の意識を育み、前向きな姿勢で本番に臨むことが、合格という最高の結果を引き寄せるのです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
では、また!
中学受験コンサルタントの野田英夫でした。